ゆめ横丁シリーズは、90年代に『詩学』に掲載されたエッセイです。
四月に生まれて
庭に桜の木があった。桜の木の下には、屍体が埋まっているとか物の怪がいるとか読むようになって、
うちの 桜の木の下には狼男が埋められていたような気になってきた。
つわりに悩まされた母が、夜な夜な桜の木の下へ涼みに出るたび、その狼男に精気をすうすう吸われて、生まれたのがこの私なのだ。
そして私は四月生まれだ。
わたしが嫁に来たばかりの頃のことだからもう昔の話だけれどとことわって、祖母は始めた。村では、こどもが生まれた家へ、お祝いによばれる前にその子を見に行く習わしなので、 その家へ行くと、産婦が、こどもの顔を被っているガーゼをめくりながら、見てやってください、
かわいそうなことをしました、と言い言い涙をこぼした。
その子はひと目見ただ けで異常だとわかった、というのだ。
昔はそういうとき、産婆さんと姑あたりでこそこそ相談して処理してしまってから、産婦には、ほんとうに残念なことだけど死産だったと告げたのだそうだ。
もう、むかしむか しの話である。
それから祖母は少しためらってから、おまえは……と言いだした。
私は生まれたとき、髪の色はうす茶色で、肌はまっ白で、しらっ子かもしれないと産婆さんに言われたのだという。それでどうしようかとみんなで悩みながら、しばらくはとな り近所へかくしておいたのだという。どうしようかと悩んだというのは、どうどうするつもりだったのだろう。これはむかしばなしではなく、いまその話をきいている私自身のことなのだ。
この話をきいたのは、母が死んだあとでのことだ。私は祖父母のペットみたいに育てられたから、母とはあまり親しくなかったままだったが、そのときは、母にもいろいろきいてみたいと思った。祖母には、他人事でも聞くように、ふうんと言っただけだった。何て言えばいいのかわからなかったのだ。
父はきげんが悪いときなにかというと、庭に桜の木なんかあるから悪いんだと、祖父のいないところで文句を言っていた。祖父が死ぬと、父はまず桜の木を切った。百姓のうちの庭にこんなものあるのはおかしいからと言いわけしいしい。
祖父がいなくなって桜の木もなくなっても、あとはみんなそのままなのに、なんだか家中がらんとしてしまってとまどった。祖母もそうとう気丈だったが祖父には全面服従だったので、私は祖母以上に祖父を畏怖 していた。その祖父がいなくなったことは、縛られていたなわがほどけたようで自由にな ったというよりなにか心ぼそかった。
ずっと祖父の陰にいた父はあまりこわくないのだ。 私は父に祖父と同じようなものを無意識のうちに望んでいたのか、あれこれ無理なわがま まを言うのだが、父は、しようがないなと言いながらたいていの事は言う通りにしてくれるのだ。ほんとは別にそんなものどうでもいいのにと思いながら、もっといろんなものほしがりながらじれていた。
私がほんとにほしかったのは、祖父がいた頃のあの緊張感だったの。
父は父で、祖父に縛られていたものがほどけたので自分のやりたいようにできる喜びといっしょにやはりその自由にとまどっていたのかもしれない。今だに私の中の男性 像は祖父だ。冷静に考えれば祖父なんてただの少し強欲な百姓じいさんで、もし今ここに いたとしたら私の好きじゃない方のタイプの人間だったような気がするが、
こどものとき の思い込みというのはおそろしい。
いま、あの桜の木は私の心の中に、祖父と同じように、本物より雄々しく生きている。 わたしがもらったからね、と祖父に言ってみる。大切にしてるからね、ほらあの頃と同じでしょ、と言ってみる。
私はこどもの頃からずうっと、四月はきらいな月だ。だから、なんでこんな月に生まれたのだろうと、自分の誕生月なのまで腹が立つ。自分の生まれた季節が好きだなんてしゃあしゃあ言う人に出あうとにくらしくなる。私ばっかり呪われてるんじゃないかと思いたくなる。
そんな月に生まれたのだからせめて名前ぐらいやさしげなものをつけてくれれば いいものを、のぶこだなんて! この頃は年とったので、まあのぶこでもいいかとあきらめて、かえってその方がよかったと思うようになったけれど、こどもの頃は、私が冴えな いのは名前が悪いからだと本気で思っていた。はるこ・ももこ・さくらこ、いくらでもあ るのに、わざわざいちばんひどい名前つけておいて、
もっとはきはきした子になれなんていったってもうだめなのだと思っていた。
まだ自分が生まれたときの情況など思ってもみなかったのだから。
さくらこだったらさくらこのようにかわいい子になれたかもしれないのにと母に言うと、花は散るから花の名前はよくないのだという。それじゃみちこは? みちは他人にふまれるからよくない。みてみぃ、○○さんのみちこさんは頭がおできだらけだから。じゃなにがいいと思う?のぶこでいいの! (自分がつけたんじゃないくせ に。知ってるんだから)
四月はきらいだけど、桜の花は好きだ。
あの満開を想うだけで心がときめいてくる。それは根が単純な証拠だなんて言われるが。まだ寒いうちから、今年こそ花見に行こうと思って、あそここことそのにぎわいを空想している。
友達にも今年こそいっしょに花見に行こうねなんて毎年言っている。相手もうんうんとただ空返事する。
そう言っていてけして行かないのだ。ほんとに四月になると、ぼおうっとしてうっとうしくて、心の中の桜の木 の下へねころんでばかりいる。ここには今も狼男がいて、その狼男にせかされて、私は彼のゆめの記述をさせられる。つまりそれが私の詩になるらしい。
________________________________________
あぶらや
屋号『あぶらや』。菜たね油やごま油でも石油を売っているわけでもない。ガラス戸に張ってある『あぶらや』と書いた紙の横に小さく、あぶら買います、と書いてある。つまりここは物を売る店ではなく、他人の無駄話を買うところなのだ。
思うに、あぶらをうるというあのあぶらは、もとはあぶなだったのではないだろうか。 あぶな絵などというあれだ。
おとうちゃんなにしてる? なんて近所へ行って聞かれたこどもが、大人の話を聞きかじったのを物知り顔に使って、おとうちゃんあぶらうってるよ、なんて言ったのがはじまりで、その話を笑いながら、自分たちも、はじめはわざとまちがえて使っておもしろがっているうちに、いつの間にかあぶらになってしまった。その方が隠語的要素も深くいっそう
ひみつめいてわくわくしてくる。これはまったく私の口からでまかせ思いつきまかせにすぎませんが、ありそな事だと思 いませんか?
あぶらやの隣はあき地で、てんとを張って、サーカスや芝居がかかった。私が初めて芝居を見たのは三つ位のときで、暗い夜道を、おぶわれていても恐くて、その背中に顔をうずめて行ったのに、てんとの中は、おてんとさまもお月さまもありったけ
の星もみんな集めてきてしまったようにきらきらまぶしくて、それだけで別世界へつれてこられたようだった。芝居は、じろうととみこという兄妹のやりとりで、酒のみの兄とその兄にいじめられている妹の話だ。その兄の役の男が、女が化けているような気がした。
次の朝起きてからも私はまだこうふんしていて、見てきた話のすじを大人たちにしてきかせて、よくおぼえてるとほめられた。それで図に乗って、あのあんちゃん、おんながおとこに化けてるみたいだった、なんて感想までしゃべった。あとになって、女役男役というのがあるのを知ってから、私にはあの頃から芝居を見る才能があったんだ、なんて、にやにやうぬぼれている。祖母にでも言ったら、無駄な金使って無駄な事する才能しかないんだ、なんていや味言われただろうけど。
やはり同じ頃、きつねの嫁入の行列を見たことがある。
うちから東の方へずうっと畑がつづいていて、その向うに山(松林)がある。ある晩、 山の裾野をちょうちん行列が通るのを、私はだきあげられて、あれはきつねの嫁入だよと教えられている。先頭に男たちがいて、そのあとによめさまとつきそいのおばさん、そ れからまた男たちが、一列に並んで通ってゆく。いくらきつねだって、いいのはああして
歩いてゆく間だけだ。むこうへ行ってしまったら、よめさんは毎日たいへんなだけだ。なんて祖母は言ったのではないだろうか。母も、半身ふずいで嫁に行かれない伯母も、これから嫁に行くであろう叔母も、それぞれの思いでそれを聞きながら、みんなで見ていたのではないだろうか。このあたりは後になってからの私の思い入れだが。
大人になってから、畑の草取りをしながら、祖母にその話をすると、そんなばかな話あるわけない、ゆめでも見たのを本当の事のようにおぼえているんだろう、と言う。でも、 あの頃は今とちがって、三才の子どもが絵空事の世界へ入れる情報なんて何もなかった。 知らないことをゆめにみるわけがない。ついでに、あぶらやの空地で初めて見た芝居の話
をすると、それは本当の事だと言う。私はあの芝居のことよりきつねの嫁入のことの方が 鮮明におぼえているのだ。というと、祖母は、それではそれは日露戦争のときのちょうち ん行列だろう、と言う。あの頃は、あっちでもこっちでも、ちょうちん行列だの旗行列だ
のがいっぱいあったから、それを見たんだろう、と言う。それで私もそのときはそう納得したのだが、最近、日露戦争は、私が生まれるずいぶん前の話だったことを知った。が、 それを言って話をむしかえしてみたい祖母はもう居ないし、あの時いっしょだったはずの
叔母とは仲たがいしているから、そんな話をわざわざしに行くわけにもいかない。したところで、昔々のおかしな話など、さっぱりわからないだろう。
この間、ひさしぶりに、あぶらやだった前を通ったら、ガソリンスタンドになっている。 おとしばなしのようだが事実だ。ずうっとあぶらやのものなのか、他人の手に渡ったのかわからないが、あぶらやには私の遠い身内が嫁入っているはずだ。学校は同級生だったが、 つきあいもないのでまるっきりわからない。もし、いまもあぶらやがあったなら、こんな話を売りによってみるのに。
変ってしまったのは『あぶらや』だけではない。そのまわりを歩いてみても、知っていた家は一けんもない。こどもの声もしない。この道をもっと行けば私の生まれた家があるはずなのだが、そのままひきかえしてきた。
── ゆめ横丁 (2) 「 あぶらや 」 ( 『詩学』 1993年5月号所載 ) ──
________________________________________
羊の首
ひゅうう!っ、とするどく、闇笛の音が頭の芯につきささってくる。羊の首が重なりあ って、宙から私を見下している。
羊を飼っていた。いちばん多いときでも十頭ぐらい。せいぜい五、六頭で、豚と同じに、 小屋飼いだった。山羊や羊は紙を食べるというけれど、うちのはどっちも食べなかった。しんぶん紙だからだめなんだよ、なんてわいわい言いながら、やわらかなちり紙をやっ ても食べない。じゃあもっと上等な半紙はどうかと、まだ使ってないそれを持ち出してき
て、やっても食べない。この羊たちおかしいよ、ふつうは食べるよ、だって本にそう書い てあるもん、なんて優等生のがき大将に言われて、私は、私自身がおかしいと言われたみたいにしょげた。
羊も山羊も、無理に口へ押し込もうとしても、口をかたく結んで顔をそむける。へんなのお!とがき大将が言って、へんなのお!とみんなが言い言い、かけ出して行っ てしまったあと、私はひとりでちらばった紙をかたづけながら、ばか!なんで食べないんだよお、と半分泣き泣き羊たちにやつあたりした。
ある日、社会科だったかの時間に、先生が、信子さんの家で羊を飼っているから、羊の ことについていろいろ聞いてみましょう、と言いだしたので、あわてた。羊は何を食べる のですか、なんて他人行儀の言葉で質問する者がいて、私はどぎまぎして、ぼーっとなってしまって、羊は何も食べません、何も食べなくても生きています、と答えてしまった。
農家のこどもはふつう、家の手伝いをするのがあたりまえなのに,私は何もしない。私 がなまけ者だからばかりでなくて、親たちが、おとなになればいやでも働かなくてはなら ないのだから、こどものうちぐらい遊んでいてもいいという意見なのだ。なのに、家庭訪 問のたびに祖母が、手伝いも勉強もよくやります、などと言うものだから、私も学校で、
祖母をうら切らないようにそんな顔していたのだ。勉強の方は、先生は本気にしていない のではないかと心配しながら、手伝いの方は信じてくれていると思っていたのだ。から、 それもうそだったことがばれてしまうのではないかと気をまわしすぎて、そっちにばかり気をとられ、いっしゅん、みんなわすれてしまったのだ。
私の答をきいて、先生が、羊は何も食べなくても生きているそうです、それで毛糸がたくさんとれて、いいセーターが着られて、いいですね。みなさんも家へ帰ったら、この話を家の人にして、羊を飼うようにすすめましょう、と言った。
家へ帰ってこの話をすると、いくら何もしないからといったってと言い言い祖母は、私を大なべのそばへつれて行って、ほら、この麦とじゃがいもを煮たのと草を食べているのだ、と言った。言われてみれば知っていたのだ。毎日、さし渡し一メートル近くもある大なべで麦とじゃがいもを煮ていることも、親たちが草を刈ってくる事も。それから私の本当の心配が始まった。私の言った事を本気にして、羊を飼う家があったら、どうしよう。羊に餌をやらないで、
そのうち死んでしまったら、私はますます先生の信用もなくなり、友達にも仲間はずれにされるだろう。その内、級だけでなく、学校中に私の悪いうわさが広まって、私はどんなひどい目に合うかわからない。そればかりではなく、大人たちが家まで押して来て、父が
責められた上、弁償させられるだろう。あした学校へ行って訂正すれば、まだ間にあうかもしれないが、とてもそんな勇気はない。とうとうだまったまま、それからしばらくは、びくびくしながら学校へ行っていた。が、 いつになっても、羊を飼ったという者もいないで、いつの間にか忘れてしまった。
羊は、毛を刈ったあと、おたがい、とつぜん姿の変ってしまった相手を敵視して、頭と頭でつつきあう。人間なら、髪の型が変ったって、新しい服を着てきたって、見まちがうことなんかないのにと思うと、おかしくもあり、かわいそうな気もした。毛糸加工場の人が毛を集めにくるとき、色見本帳を持ってくる。が、出来上ってくると
たいてい、注文した色とちがっている。こんどはあんな色のセーターが着られるとたのしみにしていたのに、がっかりする。文句を言うと、こっちの方がずっといい色だ、と、工場の人も、親たちまでそう言い張る。
今になって思うに、色見本の方は化学染料で、でき上ってきた方は自然染料だったのではないかと思う。化学染料の方が高価な時代もあったのだ。そしてこどもは鮮やかな色の方が好きなのだ。
近所に住む伯父が来て、肉が食いたくなったな、と言って、俺がやるよ、と言えば、羊を殺して食べるということなのだ。選ばれるのは、年老ってしまったのか、たくさん生まれすぎた仔羊の中の一番弱々しいのかだ。豚の方がいいのだが、豚は、許可なしに殺せないのだ。羊だって、多分同じだと思うが、
羊を飼っている家はめったにないし、食肉用に飼っているわけではないので、だれもそんなこと考えなかったのだろう。しろうとが殺すので、そのときの悲鳴が、耳の中に入ったまま残ってしまう。羊の首は、うら山へ埋める。夜になると、その首が泣いているような気がする。
肉は山もりあって、近所中へくばって、家へもみんなを呼ぶ。が、私はとうとう、羊の肉は食べられないままだ。自分の家の羊だからばかりでなく、あの独得の匂いが、おそる おそる一箸口に入れたねぎにまでしみついていて、ねぎさえ食べられなかった。
ふえすぎたといって殺し、父や伯父の気分で殺し、うら山の首はふえてゆく。その毛皮は洗ってから、別に何に使うわけでもなく、ときどきままごとや人形遊びに使ったぐらいだ。
宙から羊の首に見下ろされている。毛皮が、紙飛行機のように、あとからあとから飛んでゆく。
また、闇笛の音が頭の芯につきささる。頭痛が始まるのだ。
── ゆめ横丁 (3) 「 羊の首 」 ( 『詩学』 1993年7月号所載 ) ──
________________________________________
花子
夏休みとか春休みとかになると、しょっちゅう、花子とおたがいの家へ遊びに行ったり 来たりしていた。学校をはさんで、私の家は東へほんの少し行った、学校と同じ部落内にあった。のに、 花子の家は、西へどこまでも行って、家並が切れたあと、畑があって、その次に森をぬけ
なければならない。夜は大人さえ通るのが恐ろしいというほどで、こどもには、ひとりで通るのはひるまさえ怖い。手をきゅっとにぎりしめて、下むいて小走りに通りぬける。いっそかけ出してしまいたいのだが、かけ出せば、ほんとに何かが後追って来そうでよけい 怖くなるのだ。やっとそれをぬけ出て、また畑がつづき始めた左手に細い道が並んでいて、
その三本目をまがってくねくね行くと、花子の家へつきあたる。森をぬけるともう見える のだが、見えてるくせに、ちゃんと行くのはとてもむづかしいのだ。
まちがわないようにちゃんと数えて、三本目をまがったつもりなのに、しばらく行くと、 なんだか花子の家からどんどん遠くなってしまうときがある。しかたがないので、ひきかえしてくる途中の畑に、さっきはいなかった花子のおばあさんがいて、笑いながらこっちを見ている。またまちがえたね、この次の道だよ、という。またあるときは、一本先の道
を入ってしまうときがある。まちがえて引き返してくるたびいつも途中に花子のおばあさんがいるのだ。これはとうとうだれにも言ったことがなかったのだけれど、あれは、森の中に住んでるきつねのしわざだと思っていた。が、そんなことだれにも言えない。言えばもう、花子とも友だちでいられなくなりそうな気がした。だから家の人にも道をまちがえ
たことなど言ったことがない。花子のおばあさんもだれにも言わなかったらしい。あのおばあさんそのものがきつねが化けていたのだ。だから本当のおばあさんは、私が道をまちがえることなど知らなかったのだ。
花子の家は、開拓地の中にあって、開拓地の子供達は、集団で学校へかよっていた。近所に友達も同級生もいくらでもいたのに、おく病でおっくうがりの私が、あんな遠くまで一人で遊びに行き行きしたのは、よっぽど花子が好きだったのだと思う。
東京へ来てから、先に東京へ来ていて、もう東京なれしていた花子と、また逢うようになった。あなた、いまだにやさいしか食べないんでしょ、と花子が言った。それじゃだめよ、やさい人間はね、どうしても他人より先へ出られないわよ、あたし、こっちへ来て、それが わかったから、意識して肉ばかり食べるようにしたの、あたしもやさい人間だったから、
初めは大変だったけど、いまは肉が大好きよ、人間も変ったわ、もちろん自分から変えたのよ、あなたもこれからは今まで通りじゃだめよ。が、とうとう私は、やさい人間のまま通してしまった。本物のものぐさなのだ。
あなた、石に興味ない? と花子が言った。石? 私はすぐに、近くの乾物屋のおじさんが店先で、つけ物石そっくりなものをいつもみがいている姿を思った。あんなものあんなことしてどうするのだろうと思い思い、ひとに聞いてみたら、今流行ってるらしいわよ、 と言うのだけれど、どう見ても、一斗樽のつけ物の重石だ。花子もあんなことしてるのか
な、と思っていると、小さな箱を開けて、これよ、と言う。みどり色に光る首かざりだ。
えっ? あっ! そうよね、宝石だから石だもんね。私は、自分の勘違いにおかしくなった。えっ? なあに? ううん、なんでもない、あたし、首かざりだめなの、たまにそういうものして歩いてみたいんだけど、重くてすぐ頭痛がしちゃうのよ。これ、あなたに似合うと思って選んできたのに…。聞けば花子は、宝石鑑定士の資格を持っていて、セールスもしているのだという。
花子から、展らん会の案内状が来た。画廊の地図もちゃんと書いてある。それで、行ってみたのだけれど、見つからない。地図の通りの場所に、ちゃんと画廊はあるのだけれど、
名前が、似ていて違うのだ。そして別の人の個展をやっている。それでも思い切って、花子の名前を言って聞いてみたのだけれど、わからないと言う。私は、あの、花子の家へ行く道の途中のことを思いだしていた。花子は、あんなに一生懸命都会人になろうと努力しているのに、あのきつねにまだまとわりつかれているらしい。こんな所でまで、まだ私を化かしている。まとわりつかれているのは、花子ではなく、私?─。とうとう画廊は見つからないまま、そのことを花子に言わなかった。どうしてか、言えなかったのだ。花子からも、そのことについて、あと何も言ってこなかった。
花子が脳内出血でたおれた。いろいろあって、五年近くも苦しんで、死んだ。あなた、あたしがこんなことになってしまって、かわいそうだと思ってるんでしょ。花子の声が、なまあたたかい風になって、耳の中へ吹きこんでくる。そんなことないよ、うん、早すぎたとは思うけど、花子は何でもやって何でもできたから、きっとおばあさんなんて似合わなかったと思うから、この頃うらやましく思っているくらいだよ。そうよ、わたしはこれでよかったのよ、ほんとよ、世間ではわたしの事、よく言ってないらしいけど、
自分が何も出来ないのを棚にあげて、何もしないのがいい人間みたいな顔しているなんて
最低よ、あなたにもほんとはそういう所少しあるんでしょ。うん、そうね、花子のまねはできっこないし、したいとも思わなかったわ。展らん会もほんとにやったのよ、あなたがさがしまわったその次の通りだったのよ、言おうと思っているうちに病気になってしまったのよ。うん。わたしは精いっぱいやってこうなったんだもの、満足よ、と言い言い、花子が泣いている。
自分の家の墓まいりのついでに、花子の実家のあたりへ行ってみた。あの森はもう無くて、大きな会社になっている。花子の家のあたりも、今は街だ。今日じゅう歩いても、私には、花子の実家をさがし出せそうにもない。もう、花子のおばあさんもとっくにいない。
── ゆめ横丁 (4) 「 花子 」 ( 『詩学』 1993年8月号所載 ) ──
________________________________________
ねこのたまご
ネコノタマゴは、黒いマントを着て黒いコーモリ傘を杖の代りについて通る。ネコノタマゴは、こどもに、ねこのたまごをくれると言ってだますのだという。ネコノタマゴは、うちの前を通るとき、庭まで入ってきて、祖母と話をしたりする。こ わくないの?ときくと、おとなだからだいじょうぶだという。
ねこのたまごって、ほんとにあるのかな?と言うと、そんなこと言うとネコノタマゴに つれて行かれてしまうという。だけど、ねこだってたまご生むのかもしれない。ねこもにわとりもいろいろ似ているとこあるもの。ねこのたまごもまるいのかな?どんな色してる
のかな?ねえ、おとなならだいじょうぶなら、二人でいっしょにネコノタマゴんちへ行ってみようよ、と言うと、祖母は本気で怒りだした。それでも私はしつっこくねこのたまごにこだわりつづけた。ネコノタマゴが、いい天気ですね、などと言いながら庭へ入ってくると、私は何か言ってしまいそうで、口をおさえていると、その言葉が鼻から出てしまいそうになって、大急ぎで家の中へ逃げ込んだ。あとで、私の心を知らない祖母は、そんなにこわがらなくてもだいじょうぶだから、と、おかしそうに言う。
ねこのたまごってあると思う?と、友達にきいてみると、あの水門番のおじさんのこと ?という。ねこのたまご見てみたいと思わない?えっ?そんなものあるわけないよ、ふざけて言ってるだけだよ、と言う。そうかなあ、あたしはあるかも知れないと思うよ。うふふふふ、と友達は笑う。
ある日、祖母の手の上に、うすみどり色のたまごを見た。ねこのたまごだ!と思った。
それ、どうしたの?買ってきたのよ。ねこのたまごは売ってるの?まだそんなこと言ってる、これはねこのたまごなんかじゃなくて、瀬戸で出来てる種たまごだ、と言う。そのたまごをにわとり小屋に置くと、にわとりがまねをしてそこにたまごを生むのだという。わたしはそのたまごを持たせてもらった。こわれるから落とさないようにと言われて、おそ
るおそる持ってみると、ふつうのたまごより重い。このたまごからは、きっとこんな色のねこが生まれるのだ、と思いながら、ゆっくり持ってみた。
祖母がとり小屋からたまごをひろうたび、あのたまごはどうしてるときくと、ちゃんと置いてあるよという。
うちの黒いねこに、おまえはたまご生んだことあるか、ときいてみた。ねこは知らんぷ りしている。うちに、そのうちうすみどりのきれいなねこが生まれるよ、たまごから生ま
れるんだからね、おまえなんかよりずっといいねこだよ、と言ってやった。その黒いねこがこどもを生んだ。どこにでもいるようなぶちねこが三匹。いくらさがしてもたまごのからはみあたらない。おまえはたまごからじゃないからこんなこどもしか生まれないんだよ、せめておまえに似てればまだよかったのに、と言ってやった。うすみどり色のたまごはまだ孵らない。
村にはめったにないことだが、級に新しい転校生が来た。少しおかしな男の子だ。先生に何を言われてもにやにや笑っているだけで、口もきかない。本を読めと指されても、本を持って立つのは立つのだが、字が読めないらしい。その子は、ネコノタマゴの家の子だという。さらわれてきたのだろうか?
家に帰って、祖母にそれを言うと、ネコノタマゴの所にお嫁さんが来て、そのつれ子だという。そのお嫁さんというのは、東京者のような上品な人で、きれいな娘さんとそのお かしな男の子との二人の子持ちなのだという。どこから来たのかきくと、ネコノタマゴも 他所者だから、どこかへ行ってひろってきたのだろうという。お嫁さんやこどもをひろっ
てくるなんて。そんなものが落ちてるところがあるなんて。そんなことが出来るネコノタマゴのことをあれこれ考えて、私の妄想ははてしなくひろがってゆくばかりだ。
その子はしばらく学校へ来ていたが、だんだん休みが多くなり、しまいにはとうとう来なくなってしまった。ネコノタマゴが学校へ来て、いくら学校へかよわせても何もおぼえて来ないから、わしが家で教育するから、とことわりに来たという話だ。そしてその子は ネコノタマゴと一緒に畑仕事をしたり、魚つりをしたりしているらしいという。
ネコノタマゴのお嫁さんと娘さんがうちの前を通った。庭先で仕事をしていた祖母に、
ていねいにあいさつをして通った。通りすぎてから、私は道まで出て、その後姿を見ていた。二人ともとてもきれいな人だ。見えなくなるまで見ていた。祖母に、そんなまねするなと叱られた。それから何度も何度も通り、いつのまにか、ずっと昔から知っている人のようになった。娘さんの名前はかな子さんだということもおぼえた。かな子のね、ブラウスを買いに行くのですよ、などと話しこむようになった。うちのアキオちゃんもね、学校に行くといいのですけれど、おとうさんのあとばかりついてあるいていて、しようがないのですよ、などと言うようになった。
ネコノタマゴの家が火事で焼けて、ネコノタマゴとアキオちゃんが焼け死んだ。お嫁さんとかな子さんは、どこかへ泊りに行っていて、帰って来てからそれを知ったという。二人はずいぶん調べられて、いろんなうわさも立ったけど、結局、たまたま女の人達がるすの間の、ネコノタマゴの火の不仕末ということになったらしい。
ネコノタマゴはずっと一人で暮らして来て、それでもいつも身なりもちんとしていて、 火事など一度もだしたことなかったのに。
かな子さんが、いい所へお嫁にきまって、あの日も、二人はそのことで他所に行っていたのだという。二人は遠くへ引っ越して行くのだという。二人がうちの前を通って、庭まで入ってきて、長い間お世話になりましたとあいさつした。しあわせになってくださいと祖母もおじぎした。私はまた道まで出て、その姿が見えなくなるまで見ていた。
うすみどり色のたまごは、とうとう孵らないまま、その後の行方は記憶にない。
── ゆめ横丁 (5) 「 ねこのたまご 」 ( 『詩学』 1993年9月号所載 ) ──
________________________________________
サーカス
どどどどどん、どどどどどん。枕につけている左耳のずうっと遠くから、太鼓の音が響 いてくる。どどどどどん、どどどどどん。今時分、そんなわけがないと思いながらも、ど どどどどん、どどどどどん、私がその気になるまで、いつまででもこうして鳴らしながら待っていると言っているように、こっちの心をゆさぶりつづけるので、無視できなくなってくる。
東口の戸を開けると、月光に白く照らされた道が向こうまで続いていて、太鼓の音はその先の方からしてくる。私はその道を歩いて行く。どどどどどん、どどどどどん。ずっと 昔、これとおんなじ音を聞きながら、こんなふうに歩いて行ったことあったっけ。ただ、 あの頃は、一人ではなかった。
どどどどどん、どどどどどん。それはサーカスが来たしるしの太鼓だ。あれは、ばかだら来い、ばかだら来いと言っているのだ、と蛮さんは言う。そんなのうそだと思っても、
どどどどどん、どどどどどん、そう言われれば、そう聞えるような気にもなってくる。だから、そんなにサーカス見に行きたがるおまえはばかなしょうこだ、と蛮さんは言う。それでも私はサーカス見に行きたくてたまらない。それで私達は、おとなのだれかにつれられてサーカス見物に行く。どどどどどん、どどどどどん、行くみちみちも、太鼓は呼びつづけている。私には、いそいで来い、いそいで来いと言っているように聞こえる。なのに蛮さんは、ほら、まだあんなにおまえのことをばかにしているよ、それでもおまえは行きたいかと言う。じぶんだって同じなくせに、と私は言い返す。おれはサーカスなんかきらいだよ、だけどおまえがかわいそうだからいっしょに行ってやるだけさ、と言いながら、
本当は蛮さんの方がよっぽどうれしそうな顔して、みちみち私達はもうサーカスの中に居て、二人で開幕前の道化を演じながら歩いて行く。サーカスが来る頃は、たいてい寒い風が吹いていて、着ているものも、たびもげたもみんな新しい。まっ白いうさぎのえりまきの、おずおずした獣の匂いが鼻をくすぐったりしたっけ。
今、こうして歩きながら、しきりと蛮さんのことばかり思っている。蛮さんの口笛をほしがったりしたのも、あの頃だったろうか。やるから取ってみろと言って、大きくあけた口の中のどこにも、笛なんか見あたらない。どこへかくしたの?どこ
へもかくさないよ、ほら、よくみつけなよと言って、もっと大きく口をあけて、あははははと笑ってから、またひゅうひゅう吹きだす。私は泣きだす。だってこれはほんとに何もないんだから、ほら、口をこんな恰好にしてひゅうひゅうやれば、ほら、な、だれにだって鳴るんだ、おまえも自分でやってみろ。やってみても、ちっとも鳴らない。私は怒って家へ帰ってしまったっけ。私の口笛が、ちょこっと音が出るようになったのは、蛮さんがおとなになってしまって、もう私のことなど相手にしてくれなくなってからだ。
蛮さんはこどものくせに、ラヂオだって作れたんだ。小さな箱の中は、ぐるぐるまいた蝋線だらけなだけなのに、耳にあてると、ちゃんと音がきこえた。グライダー作りも、だれより上手だったし、蛮さんは、何でも出来る人なのだ。なのに、いつも姉さんに叱られていた。ぐずぐずぐずぐず、文句ばっかり言っていて、あの姉さんが、蛮さんにやさしくしている所など見たことなかった。私だけのときはやさしい姉さんなのに。いくら何を言われても蛮さんはだまっていて、姉さんの姿が見えなくなると、私の顔をみて、えへへと笑う。それで私もほっとする。あるとき、蛮さんが学校から帰ってきても学生服をぬがないでいたので、姉さんが文句を言うと、今日は一日中、服を取り返えてはいけない日なのだと言った。蛮さんが姉さんに言い返しをするのを、初めて見た。どうして?と姉さんが
聞き返す。おれは知らないよ、先生がそう言ったんだ。今日はいちんちずうっと学生服を 着てなさいって?!そうだよ。学生服を着たままの蛮さんは、とても偉そうに見えた。あれは何だったんだろう。あの頃は、学校にそんな日があったのだろうか。
どどどどどん、どどどどどん。太鼓の音がだんだん近くなってくる。
裏庭の、昔の羊小屋の前で、蛮さんが大きなテントを張っている。いまサーカスを見せ
てやるからな、と言う。サーカス?うん、サーカスなんかもうずっと見てないだろう。うん、そういえばもうずっと見てない、見てないことも気にならないくらい、サーカスのことなんて忘れてた。そうだと思って、おれ、今夜おまえのためにサーカスやってやることにしたんだ、と言う。今はまだ秋で、ほんとのサーカスの季節には少し早いけど、もうとっくにいないはずの羊たちが集まって、べえべえ興奮している。羊の数はあとからあとから増えて、もう本物のサーカスの雰囲気だ。けど、サーカスの人達はどこにいるの?テン
トと見物人だけあったって、肝心のやる人がいなければしょうがないじゃないの。それは おれたちがやるのさ、と蛮さんは言う。あんなにサーカスに夢中になったときがあったんだもの、できないわけないさ。もうずうっと前からおれそう思ってたんだ。こんなでっかいテント、すぐってわけにはいかないんだぞ。おれはずうっと一人で準備してきたんだ。
それで今やっと出来たのさ。だからおまえだって何かやれ。失敗したっていいよ、ここにいるのはおれ達と羊達だけだもの。 そんなこと空想したことがないわけじゃないさ。ゆめみるときって、だれだって実際の自分なんて忘れてしまうものだもんな。縄とびも鉄棒もできない私なんてもうどこかへ行ってしまってさ、空中ブランコひらひら乗っているのさ。
私は梯子を登ってゆく。登っても登ってもはてしないほど高い梯子。登りながら、私はだんだんサーカスのスターになってゆく。羊たちが歓声をあげている。私は両手をひろげてにこやかにあいさつしてから、とぶ!
私は落ちてゆく。よく見るゆめの中。落ちた場所も、いつもの水の涸れた古井戸の底。 どどどどどん、どどどどどん。
左耳のずっと遠くから、太鼓の音がまだ響いている。
── ゆめ横丁 (6) 「 サーカス 」 ( 『詩学』 1993年10月号所載 ) ──
________________________________________
くれよん
初めてくれよんを買ってもらったとき、私はただ見とれてしまった。きっと、画用紙ももらって、これに何か描いてみなさいと言われたのかもしれない。その前に絵本を買ってもらっていた。その内容は今でもおぼえている。なにしろ「本」との初めての出会いだったのだから。
〝ミコチャンハ/オハナヲ カキマシタ/トテモジョウズニ カキマシタ/
ナコチャンハ/グルグルグルグル オダンゴバカリ/チガウワヨ/イイモノ〟
という文章といっしょに、おねえさんらしい子が花の絵を描いているところと、妹らしい子がただぐるぐる落書きをしている絵本だった。叔母は何度も何度もそれを読んでくれた。終いには 私がそれを暗記してしまって
〝ナコチャンハ グルグルグルグルオダンゴバカリ チガウワヨ イイモノ〟
なんてばかにしたようにとなえながらけらけら笑ったりしたので、叔母は、私が絵を描くということを理解したとでも思ったのかもしれない。それでくれよんを買ってくれたのだろうと思う。が、不器用な私は、絵本の内容と自分の行動を同次元で考えるなんて、思ってもみなかったのだ。私はただ「くれよん」にだけ気を取られてしまっ
た。箱から一本一本取りだしながら匂いをかいだり、あっちこっち並べ変えたり、ごろごろころがしたりして遊んだ。そして、同じ色でぐるっとまかれているくれよんの着物をはがして裸にしていじくりまわした。
ある日庭のえん台の上で、いつものようなくれよん遊びをしたまま置き去りにして、ひるねから覚めて行ってみると、くれよんが太陽の熱でぐにゃぐにゃに溶けていた。私はその思いがけない変容におどろいた。とても「悪い事」をしてしまったような気がした。おそるおそるさわってみると、さっきまでのくれよんとはちがう感触で、私の自由になってくれない。くやしさと腹立たしさで、わざとつぶした。
別の色とまぜあわせて、どろだんごを作るようにこねたりした。だんだん私の遊びはそっちへ移って行った。もうそれはくれよんではなくなってしまった。その間の叔母のことは記憶にない。くれよんが、だれに、どう仕末されたかも記憶にない。
その次にくれよんを買ってもらったのは学校へ上るときで、いろいろな学用品といっしょに、これがくれよんと渡されたとき、もうあのときのようなときめきはなかった。あの
ときのせいというわけでもないかもしれないが、それは十二色しか入ってない堅くて色もうすっぽい、今で言うパステルカラー風の「アオゾラクレヨン」というのだった。たいていだれも同じようなものだった。中に、三四人、「王様くれよん」という、色も濃いし、 数も二十四色もあって、なまえの文字も漢字とひらがなで書いてあっておとなっぽい、
「アオゾラクレヨン」から見ればほんとうに王様のようなくれよんを持っている者がいた。 となりの席のA子のも王様くれよんだった。それには金色も銀色もあって、私はうらやま
しかった。図画の時間、先生が黒板に船の絵を白黒で描いて、みんなこれをまねて描くようにと言った。私は画用紙に黒いくれよんでそれを描いていた。するとA子が、黒じゃなくて白で描くのだ、先生のを見てみい、白で描いてあるから、と言う。先生は黒い所へ描くのだから白で、私達は白い紙へ描くのだから黒でいいのだということを、A子に説明し
たいのだが、言葉がうまく出て来ない。A子は続けて、おまえのは白い色がないからできないんだろうと言う。先生に見せたらおまえはおこられると言う。たしかに私のには白がない。と、なんだかA子の言うことの方が正しいような気がしてきて、まわりの人のをのぞいてみると、みんな黒で描いている。そう言うとA子は、それは白を持ってない者だけだと言う。描き終ってからおまえに白をかしてやると言うのを、いいとことわった。それはA子になんか借りるのがくやしかったからなだけで、ほんとうは、黒でいいのか白で描くべきなのか、もう私にもよくわからなくなってしまっていた。
あれは、三年生だったかの、もうすぐ夏休みに近い暑い日だった。たいていいつもだれか友達と一緒なのに、どうしてかその日は一人で帰る、途中のことだ。だれかうしろから 来る足音に気がついた。おとなではなく、こどもなのは、気配でわかる。私を追い越しもせずはなれもせず同じ間隔でついてくる。いつまでたっても声もかけないところをみると、
私と親しい者ではないらしい。ふりむいてみる勇気はない。かけ出すこともできない。気にしないふりで歩いて行く。横へ入る道がある所に来たとき、とつぜん名前をよばれた。 四郎だ。どきんとしたが、平気をよそおって返事をした。くれよん持っているかと言う。 私の恐怖はてっぺんに達した。持っていると言えば、借せと言うのだろう。借したら最後、
返してなんかくれないにきまっている。四郎は評判の悪い子で、くれよんは貴重品なのだ。 持ってないとうそをつきたいのに、私の口は勝手に、持っていると言ってしまっている。
もうだめだと思って、大声で泣き出しそうになった。が、四郎は何も気づかずに、そんならいいんだと言った。俺たち上級生は、先生に申し込めば学校で買えるから、もし持っていなければ買ってやろうと思ったんだ、持ってんならいいんだ、それから、何か困ったことがあればおれに言え、何でもしてやる、と言って、横への道をまがって行った。私はほっとすると同時に気がぬけて、しばらくぽかんと立っていた。それからみちみち、ああよかったと思い思い歩いているうちに、なんだか四郎に悪い事をしてしまったと思って、すまない気持ちになってきた。みんなが言うほど悪い人ではないのかもしれない。よく知りもしないで、他人の言うことだけ本気にして、せっかくの親切にひどいことをするところだった。もし、持ってないとうそをついていたら、きっと話しているうちに、うそがばれて、四郎にいやな思いをさせるところだった。が、うちの人にも友達にも、だれにもそのことを言わなかった。なんだか、四郎なんかにはなしかけられたなんてことを知られるのがいやな気がしたのだ。
四郎は大人になって、北の方の遠い所でオルゴール作りになったという話をきいた。あるとき、オルゴールを作っている囚人たちの姿をテレビで見た。四郎とそれは関係がないのかもしれないが。
________________________________________
砂道
とろとろおかゆを食べている。母を煮たおかゆを食べている。さくら色の塩をふりかけて食べている。だれか戸をあけて入ってきて、おかあさんの具合どう?ときいている。ゆうべ死んだの。やっぱりな、あんたが殺して食べているといううわさだから来てみたんだ
けど、やっぱりね。ちがうわよ、病気だったのよ、ずうっと病気でいて、とうとうゆうべ死んだのよ、だからわたしがおかゆにして食べているのよ、だってわたしは長女ですからね、ちゃんと後仕末しなくちゃならないでしょ。そう言って、わたしは母を食べつづけている。少し砂がまじってるみたいねとつぶやくと、来るとき砂道を通って来たからね。母がおかゆの中からそう言う。砂道かあ、なつかしいなあ、あの辺変ってない? 昔のままだよ、いつもきれいな砂が敷いてあるよ。ほら、また砂つぶ。
あれは不思議な道だ。どんな大雨のあとも大風のあとでも、いつもきれいな砂が敷いて ある。そのくせ砂を敷いているところなど一度も見たことがない。まるで魔法の砂敷人夫 でもいるように。だから道そのものも現実ばなれしたいい道なのだ。
ゆうべは大雨だったもんで、ほれ、こんなに泥がはねあがってしまったよ、なにしろ心配で心配で大急ぎで来たからね。さっき来た人がそう言っている。砂道を通って来ればよかったのに、と私は母を食べつづけながら相づちしている。砂道ねえ、そういえばそんな 道があったねえ、今でもあるのかねえ、いちいち砂を敷くよりも舗装しちゃった方が早い
もの、もうとっくにコンクリート道になってしまったんじゃないのかねえ。でもかあさん はここへ来るのに砂道通って来たんだって、だから、ほら、このおかゆに砂がまじっている。これ、砂道の砂なんだって。おや、そうかい、どれどれ、…ああ、ほんとに。と言い言いその人も母を指ですくってなめている。ふくふくしておいしいね、この甘味もとても
いい、この人は美人だったからね、だからこんなにおいしいんだよ。みんなそう言うよ、
そうしか言わないんだ。いいじゃないの。淋しいよ、こどもとしてはね、あんたたちのこと気狂いのように心配していたとか、ね、言ってほしいよ。心配していたにきまっているでしょ。そうでしょうけどね、きれいでおとなしい人なんての、母親像としてはね、母親なんてものは、もっとすごみのあるこわいものだと思うよ、ほん気でこどものこと思ってたらね。あんたんとこは強すぎるおばあさんがいたからね。わかってるわよ、今じゃこの人よりわたしの方が年いってしまったんですからね。そうよ、だからこうして、私は母を煮て食べるほか、どうしようもないのだ。そう、あなたの言う通り、わたしがこの人を殺したのかもしれない。単なるうわさよ、うわさなんてろくなものないからね、気にしない方がいいよ、わたしだって本気でそう思って来たわけじゃないのよ、ただ心配だから、おまえのことがね、おばさんとしてね。どのおばさん?あなたは本当にだあれ? どのおばさんにもこのおばさんにもおばさんはおばさんにきまっているでしょ。
食べても食べても母は減らない。ねえ、あの人知ってる?おばさんだって言ってるけど。
だれもいやしないでしょ、ずっとおまえとわたしと二人きりだよ、こうしておまえに食べられるの、とてもいい気持ちだよ。食べてるうちにだんだんかあさんのことわかってくるよ、かあさんはどうしようもなかったってこともね、わたしが薄情すぎる娘だったってこともね、かあさんに許してもらいたいからゆっくり時間かけて食べるね。ついでにおまえもみんな許してしまいなさい、今さら何を言ってもすんだことなのだから、そうすればその変なおばさんなんかけして現われなくなるからね、だれも悪くなんかないんだから。
砂道には、一枚の写真のような思い出がある。いくつぐらいだったのか、もう学校へ上っていたのか、そのへんもあやふやなのだけれど、ゆい子ちゃんと私が砂道を通って行くと、向こうから大きな女の人が来る。れん子さんだ!下むいて!とゆい子ちゃんが私に言って、二人で下むいて通りすがろうとすると、大きな女の人が、ゆい子ちゃん!そんな遠くの方の子と遊ばないで、うちのたえ子と遊びなさい!とどなった。ゆい子ちゃんと私は一瞬、きゅっと手をかたくにぎって立ち止まった。大きな女の人はそれだけ言うと、あとはぶつぶつ口の中で文句を言いながら行ってしまった。それだけのことなのだけれど、な
んでこれっぽっちのことをこんなに鮮明にいつまでもおぼえているのだろう。今では思い出すたび一人でおかしくなってくる。だって遠くの方と言ったって、ゆい子ちゃんちがあって大女の家があって、その間に蛮さんのうちがあって、その次が私の家なのだ。この大女は蛮さんのうちへ遊びに来ることもあって、たまたま私が出くわしたとき、蛮さんがいないときを見て、なんであたしんちのとなりへ遊びに来たとどなられたこともある。
砂道でね、あかい粒の薬が二つ、ぶつかったりしながら遊んでいてね、わたしも入れてと言ったら、わたしたちはおまえに飲んでもらえないからこうしてふたりで遊んでいる遊
びしているのよと言うのよ、あれ、かあさんが持ってた薬だよね。わたしが生家(うち)から持って来た薬でね、子供の頃、熱の出るたびあれを飲まされてね、あれを飲むと、別に熱が下るわけでもないのに、不思議と安心してねむれたのよ、嫁に来るとき、ははおやが持たせてくれてね、おまえが熱を出すたび飲まそうとしたのだけれど、おまえはあばれてけして飲んでくれなかったのよ。なぜ無理にでも飲ませてくれなかったの? わたしがいくじがなかったからね、だめな母親だったからね。あの頃あの薬飲んでいたら、わたしどんなふうな人になってたかな? 変らないでしょ、そんなにはね。わたしの薬ぎらいはあのせいじゃないしね、おばあさんと叔母さんに無理やり飲まされた白い粉薬のせいだからね、だまされてね、叔母さんの赤いハンドバッグあげるからってね、これ飲んで早くなおって、
赤いハンドバッグ持って、いいとこへつれて行ってやるなんてね、それでも泣き叫んで、いつも最後に無理やり飲まされたっけ。母さんのおかゆ食べ終ったら、砂道で遊んでるあの二粒のあかい薬飲みに行くね、おいしいって飲むからね。砂ついたままね。
── ゆめ横丁 (8) 「 砂道 」 ( 『詩学』 1993年12月号所載 ) ──
________________________________________
美三郎
檻の中にはふとった赤ずきんちゃんがねむっている。狼は? そんなこと私は知らない。 だって私は今、その赤ずきんちゃんのゆめの中にいるんだから。
今日は美三郎の誕生日のはず。だってゆうべ私が床の中でねむれないでいたら、美三郎という名前が何度も何度も茶の間の方からきこえてきたもの。美三郎はめったに家に依りつかない。この前帰って来たのも去年の誕生日の前の日だった。美三郎ときたら、誕生日のお祝いしてもらうのだけが楽しみで生きているようなやつだからと、父がそう言っている。美三郎は、どこで何して暮しているのか、いくらきいてもにやにや笑いながら、てきとうにやっているよと言うだけだ。もしかするととても悪い事しているのかもしれないけど、帰って来たときは、まるで毎日この家からつとめに行っていて、いま仕事から帰ってきたのだというように何気ない仕草で座敷へ上りこむ。だからきっとゆうべもそのようにして帰ってきたのだ。だいぶ時間がおそかったのは、残業でもあったようなふうでもそもそ上りこんだのだろう。
そして今日はみんなでごちそう食べるのだ。今日は誰が殺されるのかな。父の牛か羊? まさか私の猫ってことはないわよね。あの猫は美三郎がどこかでひろってきたものだもの。もうずうっと前、どのくらいだか数えられないほど前、やっぱりいつもみたいに誕生日の前の日帰ってきたときつれてきたのだ。私は猫が大嫌いで、母だってその事知ってるくせに、そのとき、じゃあおまえがもらいなさいと言って、母は美三郎のごきげんを取っ
たのだ。母っていつもこうなのだ。いやなことはみんな私に押しつけておいて、何事もなかったようにすましている。猫は黒とらで青い目をしている。とても美男子だわって、母は、まるで人間の男でもほめるように興奮気味に言ったっけ。私はその猫にミーと名付け た。美三郎のミーなのだ。美三郎への怒りと悪意をこめて。平凡すぎない? と母が言っ
た。呼びいい名前でしょ。猫なんて呼びいいのが一番よ。ともだちんとこの猫なんかハムレットって付けたんだって。だけど全部言うのは言いにくいし、ハムハムってよぶのもあんまりよくないっていうんで、レットってよぶことにしたんだけど、レットレットって言
ってるつもりがットットになっちゃうんだって。ね、猫なんてそんなものよ。だから初めからミーが正解だよ。ね、ミー。私はねこなで声で言いながら思いきりミーのしっぽを持って宙づりにしてやった。あれから何年たったのかしら。私は今だって猫が大嫌いだ。だから母がめんどうみている。母は私のこと以上にミーを可愛がっている。だからミーも母になついている。そのミーを今夜のごちそうにするわけないよね。ほんとはそうだとおもしろいんだけど。私はもともと肉を食べないから、今夜のごちそうが猫の肉だろうと何の肉だろうと関係ない。肉そのものは食べないけど、その肉の味のしみ込んだやさいをむしゃむしゃ食べる。こういうのって偽善かな? 動物は猫だけじゃなくたいてい嫌いだ。少し
興味があるのは狼にだけ。まだ本物を見たことないけど、この家の裏の森の中にはいまだに一匹生き残っているという噂だ。狼は我家の守り神であるらしい。でも家族のだれもまだそれを実際に見たことはないらしい。村の一番年長の物知りのおじいさんさえ親から聞いただけだというし、その親という人もほんとに見たことはなかったらしいというのだか
ら、噂というより伝説かな。狼ってかっこいいよね。だから赤ずきんちゃんだって、食べられちゃいたいほど好きになってしまって、わざとあんなことしたんだと思うな。私はあそこまで好きではないけれどね。そうそう、今夜のごちそうの話ね。それは多分母が飼っているにわとりになると思う。ほんとは毎年そうなのだ。卵を生まなくなったのを一羽ね、母が首をひねって殺すの。あんなやさしげな顔してね、平気でやるのよ。よくそんな事できるねって言ったら、主婦になったらおまえだってやらなくちゃならなくなるわよ、
だって。だから私は結婚なんかしないのよ。村の者は私のこといろいろ言ってるらしいけど、あんな連中に何も言われる筋合ないわ。連中ときたら、私に近づけない腹いせにそんなことして私を辱めているのよ。母が起しに来たらしいわ。
美三郎兄さんが帰ってきたのねって母に言うと、あなたにお兄さんがいるんですか、なんて言うのだ。何言ってんのよ、お母さんたら、気でも狂ったの、今日は美三郎兄さんの 誕生日でしょ、だからゆうべ帰ってきたんでしょ、私きいたもの、美三郎美三郎って、お
母さんおおさわぎしてたじゃないの、だから今日もお母さんにわとり殺すのよね。 またも一人、母にそっくりな、白いかっぽう着みたいのを着た女の人が入ってきた。母はその人に、わたしのことお母さんとまちがえてるみたいです、と、顔をこわばらせて言っている。二人は小声で何かはなし合っている。そういえば、今朝の母はずいぶん若く見える。私より若く見える。私って今いくつなのかしら。私の誕生日はいつなのかしら。私は誕生日のお祝いなんか一度もしてもらったことないわ。だから私はとしをとれないんだ
わ。ずうっと同じとしのまま、そのとしも忘れてしまうほど長い間、毎年毎年美三郎の誕生日のお祝いを羨しがりばかりしながら生きてきたんだわ。
あなたにはお兄さんがいらっしゃるんですか、だったらきっとその内お見舞に来ますよ、ですから安心してのんびり待ちましょうね。あとから入ってきた女の人がそう言っている。美三郎がお見舞に? 一度も私の方なんか向いたことのない美三郎が? 病気でもない私を? ここはどこなのかしら? 私のへやとはちがうみたい。ここはどこなのでしょうかってきいたら、いいんですよ、そんなこと気にしなくても。ゆうべはよくねむれましたか、
なんてしか言わない。
となりのへやからうめき声みたいなものがきこえる。狼の声? それとも美三郎の声?いま私はふとった赤ずきんちゃんのゆめの中にいるのだ。とつぜん目まいがした。赤ずきんちゃんがねがえりをうったらしい
── ゆめ横丁 (9) 「 美三郎 」 ( 『詩学』 1994年1月号所載 ) ──
________________________________________
山椒魚
テレビで、山椒魚が泳いでいる風景を見ながら、胸がどきどきしてきた。どうしてなのか理由はわからないまま、その痛みはだんだん濃くなって行くばかりだ。テレビは、アップでその手を映した。褐色の体の色にくらべて、その手のひらの白さ。指の形が、人間のそれに そっくりだ。
村に沼があった。そのまん中あたりから、年中、掘抜き井戸のようにきれいな水が涌き
出ていた。だから沼の底がないほど深いのだということなのか、底なし沼なんていう不気味な名前で呼ばれていた。その沼には山椒魚が住んでいると言われていた。本当に姿を見たという人もいたし、姿は見たことないけれど、そのそばを通ると、山椒のような匂いがするときがあるのが、山椒魚の住んでいる証拠だという人もいた。
山椒魚は、体のいぼいぼから発する匂いが、山椒の匂いに似ているので、その名が付いたと、テレビで言っている。私が生まれた家の井戸端に、大きな山椒の木があって、実が成ると、薬味にしたり、 葉っぱもいっしょにつくだ煮にして、食べた。これとおんなじ匂いのするさんしょううおって どんなのかなときくと、余計なこと考えないで早く食べてしまいなさいと言われた。
この子って、熱が出るたび、山椒みたいな匂いがして、 山椒の木の祟りでもあるんだろうか、という声を聞いている。そんなことがあるもんか、 木の祟りだなんてばかなことが! だいいちあの木を粗末にしたことなどないじゃないか。 でも、ほら、この子は姿かたちもふつうと少しちがうし…。 何かの拍子に頭に浮び上ってくるそんな会話。 いまでもわたしはそんな匂いのするときがあるんだろうか。
わたしのどこがふつうとちがうんだろう。水が波立ってくる。わたしの心も波立ってくる。どこからか、 あまいあったかそうな匂いのする女の子の泣き声がきこえてくる。 あれはわたしの声? そんなはずはない。だってほら、いまわたしはここにいて、 わたしは魚だもの。心はもっと波立ってくる。手を見る。そう言えば、ここに住んでる、
ほかのどんな魚にもこんなものはないのに。だっておまえはほんとはにんげんだからさ、 という声が、波の中からする。ほら、おまえには足だってあるじゃないか、その足で歩いて、 早くうちへお帰りよ、という声が続いている。わたしってほんとににんげんなのと問い返せば、 あはははは、どっちでもないのさ、おまえはきけいだからね、あはははは、
という別の声もする。いちど壊れなければだめなのさ、とも言っている。 どうすればこわれられるの? そうか、おまえは壊れることもできないのか、 もうおまえに関心持ってる者なんかだれもいなくなってしまったからな、 ひとりで壊れるなんて芸当、おまえにはとても無理だし。
きょうは、この魚を料理しなくちゃあ。だって大切なお客さまが来るんだもの。 この魚はそのお客さまに食べられるために、あの沼でずうっと待っていたんだもの。 そう思いながら、わたしの心は波立ってくる。大切なお客さまってだれのことだったっけ? いくら考えても、もう思い出せないほどむかしの約束のような気がするのに、 待つ心だけだんだん濃くなって、わたしをせかせる。
こうしてね、あばれる魚に庖丁をつき刺すのよ、そしてすぐ料理して、 すぐ食べていただかなければならないの、前の日に釣ってきておいて、 おとなしくなってしまってから料理したり、料理ができたのに、 なかなかお客さまが見えなかったりというと、もうおしまいよ、こうしてね、 こんなふうに遣るのがこつなのよ。と言いながら、その手つきをやっているつもりなのに、
その魚はちっとも動かない。どうしたのよ、おまえはいま殺されようとしているのよ、 怖くはないの、それともあんまり怖くて動けなくなっちゃったの? 魚はだんだん固くなって、せと物細工か何かのようになってしまって、 わたしのほうが怖くなってきて、あわてだす。
そんなことしちゃ、だめじゃないの! という声に、はっとしたとたん、 魚はわたしの手から離れて落ちて行く。だから言っているじゃないの、それなのにおまえは! だってきょうはお客さまがくる日なのよ、ずうっと待っていた日なんだもの、 だから一生懸命だったのよ、わたし…どうすればいいの。
いま、わたしは落ちて行く。落ちながら、とうとう壊れるんだと思う。でも、 まだいまなら避けられる、ちょっと横へよければ間に合うんだ、と思いながら、 まだ壊れたくないと思いながら、思いを無視して、体はまっすぐに落ちて行く。 おまえはこわれることさえできないのかという声を思い出しながら、 どこまでもどこまでも落ちて行きながら、みんなだんだん遠くなって……。
テレビの中から、山椒魚がこっちへ来る。目が合う。私のどきどきはまだ続いている。山椒魚は、清流にしか住んでいません、とテレビで言っている。底なし沼は、まんなかあたりからきれいな水が涌き出ていただけで、沼全体はいつも、 泥と、どろどろした青黒い水ごけにおおわれていたから、あんな所に、山椒魚がいたとは、
とても思えない。山椒の匂いがするときがあったのは、たぶん、沼の所から坂を上ってすぐの、 私の家の井戸端の山椒の木の匂いが、風の具合で流れて行ったのだろう。だけど、 山椒魚などというもの、本当はあの辺にいるはずのない魚のことを、 だれがどんなふうにうわさし始めたのだろう。旅の行商人かが、 どこかで見たか聞いたかして来た話をしたのがはじまりだったのかもしれない。
画面は、芽吹き初めたねこ柳を映している。あの沼の岸にも、ねこ柳があった。 もし今もまだあるなら、あのように芽吹き初めているだろう。底なし沼は、まだあのままだろうか。山椒魚のうわさなんかも、まだ残っているのだろうか。私の生まれた家の、あの井戸端の山椒の木は、どうしただろう。もう井戸なんか使わないから、 有れば危ないだけだから、埋めてしまおうと思っていると、弟が言ったのは、
あれはもうずいぶん前の事だ。
── ゆめ横丁 (10) 「 山椒魚 」 ( 『詩学』 1994年2月号所載 ) ──
________________________________________
月夜茸
森がわさわさわさわさこっちへ来る。だんだん近づいてきて、みると、 その向こう側の古い家が燃えていて、炎の中で、 祖母がくねりながら燃えている。まっかに照りながら、祖母は美しい。 あの人もずうっと女だったんだなと、それを見ながら思った。 祖母は嘘をついていたのだ。女であるのは若い時だけだと、 本気で思っていたのではなく、思おうとしていたのだ。だから、
いつもきれいに髪を結って朱い玉簪などつけている祖父の妹を、 あんなに憎げに悪く言ったのも、 その自分の思いの重みに堪えかねてのことだったのだ。 祖父の妹も、そんな祖母の心を知らずにか、知っていてわざとからかったのか、 家へ来るたび、必ずあとからボーイフレンドのじいさんがたずねてくる。
あのじじいもほんとに、 と祖母は陰でぶつぶつ言いながらつっけんどんにお茶を出す。 そんなこと気にもせず、そのあと二人はそろって帰って行く。あのふたり、 どこへ行くのかなと言うと、あんな気狂いども、わたしにはわからない、 と祖母は言う。古い家と祖母の燃える照り返りで、森の中まで明るい。 森の中では、 父母と弟が酒を飲んでいる。ああ、もうよっぱらっちゃったあとはしゃぎながら、
母がしなしな溶けた。父はそれをいとおしそうに見ていてから、 もういっぱい酒を飲んで、ばたっとたおれて、すうっと消えた。 一人残った弟は、しばらく手じゃくで飲んでいたが、 なんだかねむくなってきたと言って、横になって、口から血をたらした。 死んだんだなと思った。古い家も祖母も燃えつきて、あとは静かなうす闇。 とうとうみんないなくなってしまったと言って、私のそばで妹が泣いている。
今さら泣いたってどうにもならないでしょと言っても妹は泣きつづけている。 このままというわけにもいかないから、近所へ知らせにあるく。あのお、 家の者がみんな死んじゃったものですから、 お清めのお祭りをしたいと思いますので、集まってください、 とたのんであるく。こんなになめらかに挨拶の言葉が出るなんて、 自分でも思いがけない。はじめはみんなぽかんとしてあっけにとられているが、
そのうち、それはとんだことでございましたと挨拶を返してくれて、 森の中に集まってくれた。古枝をかき集めて、まだ姿の残っている弟を焼いた。 こいつときたらほんとに最後までどじで世話やかせるんだからとぶつぶつ文句言いながら、 火箸代りの古枝で、弟をつっつきまわす。 今夜のごちそうのために茸をさがしまわっていた西の家の小父さんが、
あそこにあの白い茸がまた生えているよと指をさす。そっちを見ると、 大きな茸が五、六個ほど、白く浮き出ている。
昔も、同じものが生えたことがあったのだ。 今まで見たこともないような白い大きな茸なのだ。 近所の人たちも見にきた。こんなもの初めて見る、とだれもが言った。 なんときれいな茸だ、けど、きれいすぎてうす気味わるいと、 こそこそ言う者もいた。 何か悪いことでも起きるのかもしれないと祖母が心配した。 あんなものひっこ抜いちゃえばどうってことないと父が言った。
森の神さまの何かのおつげかもしれないからそうっとして置いた方がいいと母が言った。 さわらぬ神にたたりなしかと父が笑った。茸は、幾日してもおとろえもせず、 ひと所に十個以上もかたまって、そのまま生えていた。ある日、 通りがかりの他所者の人が来て、わたしは茸狩りに歩いている者ですが、 おたくの森でめずらしい茸を見つけました、あれをゆずっていただきたいのですが、
おいくらお払いすればいいでしょうかと言った。あんなもの、 うちではみんなでうす気味わるがって、どうしていいかわからず困っていたのです、 よかったらどうぞ持って行って下さい、お金なんて、そんなもの、 とんでもない、と父が言うと、いいえ、あれはつる茸といって、 とても高価なものです、東京の料亭あたりへ持って行くととても高く売れるのです、
と言ってその人は、父に多額のお金を置いて行った。次の年も、 同じ場所に同じ茸が生えた。またあの人が来るかもしれないと待っていたが、 とうとうその人は来ないまま、もう去年のように話題にもならず、 いつの間にか茸は枯れた。その次の年には生えなかった。 それっきりもう生えなかった。家には別に何事も起らなかった。
最近、みんなで茸狩りに行くからつれて行ってやると言われて、 後ついて行ったとき、あれとそっくりの茸に出合った。ほら、これ月夜茸、 と言って、きのこ研究家の志田さんが見せてくれたものを見てどきっとした。 うちにもそれと同じものが生えたことがあったよ、つる茸というのだと言って、 知らない人がお金を置いて持って行ったよというと、つる茸というのもあるが、
これはちがうと言う。これには猛毒があって、 こんなもの食べたら死んじゃうよと言う。でも、あれは、 これと同じものだったと思う。あの他所者は、 まちがえてつる茸だと思ったのだろうか。それとも本当は知っていて、 わざと父をだまして、いらないというお金まで払って持って行ったのだろうか。 どうして? あんな茸なんぞ、なにもわざわざ家まで来ていろいろ言わないで、
だまって取って行ってしまっても済むものを。茸狩りなんてそんなものなのに。 そんなことさえ、今になって怪しめば怪しいことだ。月夜茸は、 志田さんの手のひらの上で、見れば見るほど美しい。まるで天女だ。 天女茸と名づけたいほどだ。これが猛毒? そんなら美しい毒婦。 私の妄想が始まる。あの男(私の家の茸を買って行った)には、
殺さなければならない人がいたのかもしれない。あの茸を持って行って、 ほら、今日はこんなめずらしい茸を見つけたよと言い、あら、ほんと、 これ食べられるの? もちろんだよ、つる茸と言ってとてもおいしいし、 精もつく、なんて言いくるめて食べさせて殺したのかもしれない。今のように、 マスコミなんてものの発達していない時代だったし、 警察も保健所もそんなにやかましくなかった。
食あたりぐらいでかんたんに済んでしまったのかもしれない。 そしてそんな出来事があったことなど、我家の耳までとどかない。 有りそうな話だ。
だけど、そんなこと今ここで話す気にもなれない。 あれは森の神さまの何かのおつげかも知れないからこの仏さまといっしょに焼いちゃいましょと言って、 私はそれを取って来て、弟の燃えている中になげ入れた。 白い茸は弟より早く燃えつきた。
── ゆめ横丁 (11) 「 月夜茸 」 ( 『詩学』 1994年3月号所載 ) ──
________________________________________

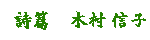 木村信子の公式ページへようこそ
Welcome to Poet Nobuko Kimura's homepage
木村信子の公式ページへようこそ
Welcome to Poet Nobuko Kimura's homepage